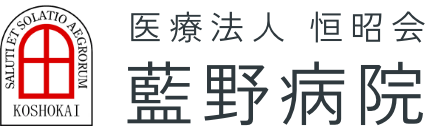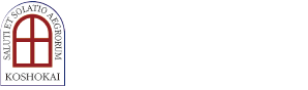お知らせ
令和7年9月28日(日)に開催しました市民公開講座の質問に対する回答を掲載しました
お知らせ
News
- 3月12日(木)に糖尿病教室を開催します
- 2月1日よりオープン検査の検査項目について一部変更いたしました
- “あいの流パーキンソンダンス®”の会~ダンスを通じて元気になろう!~第32弾
- 新しい肺炎球菌ワクチン「キャップバックス®」の接種を開始しました
- 令和8年1月24日に第23回認知症ケアスタッフのための認知症講座・認知症家族教室を合同で開...
- 入院中の患者様に処方された薬剤の未投与について
- 年末年始の面会について
- 年末年始の診療について
- 令和7年11月28日(金)あいのまちの保健室(出張版)~はつらつ長寿をめざして~を イオ...
- “あいの流パーキンソンダンス®”~ダンスを通じて元気になろう~第31弾
令和7年9月28日(日)に開催しました市民公開講座の質問に対する回答を掲載しました
令和7年9月28日(日)に行いました市民公開講座において、下記の質問がありましたので回答させていただきます。
Q1 痙縮に対するボトックス注射は保険診療で行えますか。
A1 保険診療で行えますが、痙縮の具合や身体の大きさで注射を打つ本数が違います。
Q2 第3者が認知症ではないかと気づき、同居されていないご家族に連絡して説明する場合、相談をできる所は、三島医療圏ではどこになりますか。三島地区で、地域・自治体と連携している病院は藍野病院以外に他ありますか。
A2 三島医療圏には多くの病院があり、茨木市が発行している認知症サポートブックには「認知症の相談ができる診療所と病院」「認知症の診断ができる病院」の一覧が掲載されています。また認知症サポートブックは、茨木市のホームページにも掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。
Q3 認知症への備えというのを具体的に教えてください。
A3 認知症に「ならないように」ではなく、「なったらどうするか」の備えが大事です。そのためにはどのような行政サービスが使えるのかを調べたり、将来ホームなどに入所するとしたらどういうところが良いのか見学する、などが具体的な備えです。その前に、もし認知症かな、と思ったら、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームのどれかに相談する、ということを覚えておいてください。
Q4 時々もの忘れをします。どの期間ぐらいで認知症になりますか。
A4 人間は20歳代を超えたら「誰でも」認知機能が低下してもの忘れをするようになります。もの忘れをしない人はいません。もしいたら、学校のテストで満点取れるはずです。なので、もの忘れについては気にしないことが大事です。「生活に困ったら」認知症なので、その時は医療機関、または行政に相談しましょう。
Q5 両親が2人で生活しているが、父親が認知症で母の父に対する言動が強くて厳しい。優しく接してあげてほしいと伝えるも、母より「毎日だからこちらが泣きたい」と言う。どうしたらいいですか。
A5 お母さんのご苦労もわかります。家族介護は介護する側もされる側も遠慮がなくなってかえってトラブルが増えるので、なるべく避けた方が良いと思います。介護保険などの行政サービスを利用すること、お母さんの自分の時間を優先してもらうこと、などが良いでしょう。また、接し方としても本人の意思を否定しないことが双方に楽な介護のコツですが、慣れるまでは難しいかもしれません。認知症の人の家族教室や認知症カフェに参加して、色々な情報やアドバイスを受けてみましょう。また認知症の人は、昔のことは覚えていることが多いので、楽しかった思い出話をするのがおすすめです。回想法という技法でもあります。参考にして下さい。
Q6 頭を元気にする方法はないですか。
A6 家にずっといるよりも外に出て散歩したり、会話したりすることが脳の活性化につながります。また規則正しい生活をすることも、生活リズムが良くなります。
Q7 茨木市内のいくつかのオレンジかふぇに参加しましたが、不定期開催のカフェには参加したことがありません。いつ開催するかわからないので、どうやって調べたらよいのでしょうか。
A7 参加を希望されているいばらきオレンジかふぇ(認知症カフェ)に直接お電話していただくか、茨木市のホームページに掲載している場合もありますので、ご確認ください。